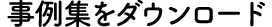- チーム名:株式会社ゆうぼく
- 業 種:牛の生産、加工、
流通・販売(6次産業) - 導入規模:39名





 農業生産の1次産業と加工の2次産業、流通・販売の3次産業を掛け合わせて6次産業と呼ぶ。ゆうぼくは1次から3次までさまざまな事業を手がけている。
農業生産の1次産業と加工の2次産業、流通・販売の3次産業を掛け合わせて6次産業と呼ぶ。ゆうぼくは1次から3次までさまざまな事業を手がけている。
株式会社ゆうぼくは、愛媛県西予市の直営農場で自社ブランド牛「はなが牛」を育て、無添加の加工品や熟成肉として直営のレストラン・売店で提供している企業です。創業は1980年、ビニールハウスの牛小屋でわずか2頭の牛を飼育するところからのスタートでした。その後、積雪による牛小屋の倒壊や、火災による建物の焼失といった苦難を乗り越え、牛の飼育数は530頭にまで増加。生産(1次産業)から加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)までを一貫して自社で行う、いわゆる「6次産業」の企業へと発展を遂げ、地元住民を中心に多くのファンを獲得しています。
しかし、実はそうした成長の陰で、同社は大きな経営課題を抱えていました。2013年に入社し、父から実質的な経営権を承継した岡崎晋也氏は、当時をこう振り返ります。
「ひと言でいえば、さまざまな意味で社内が“バラバラ”だったのです。たとえばデータの管理。弊社は長年、『無添加のおいしいお肉を自分たちの手でお客様に届けたい』という想いで経営を続けてきました。しかし、結果としてスタッフの経験や感覚に頼る部分が大きくなり、牛の状態や棚卸しの状況、売上などの情報の管理は個人任せになっていました。紙やExcelなどで個別に管理されているデータは、不足や誤りの多い不完全なもので、経営側が確認できるのは、数か月単位でまとめられる報告書だけ。当然、牛の死亡など、なにか問題が起きてもすぐには把握できません。現場の課題がなかなか見えてこないため、有効な対策を立てられず、業績が伸び悩んでいました」
(岡崎氏)
同社内は、組織やチームという面でも“バラバラ”な状態でした。同じ会社のスタッフとはいえ、それぞれの業務の場所や内容は、牧場での牛の飼育・管理、工場での食肉の加工、レストランでの接客と、部門によって大きく異なります。情報が共有されず、全体の状況がまったく見えない中、各部門が互いの業務に対してどんどん無関心になっていったのも無理はありません。皆の目が死んでいる――岡崎氏は率直にそう思ったそうです。
そうした状況を打破するため、岡崎氏は、かつてメーカーのIT部門に勤務した経験から、属人化していたあらゆることの合理化・データ化を進めていきます。それによって、確かに業績は上向き始めました。しかし、従来のやり方を否定するかのような若き次期社長の経営方針に、スタッフからは反発が……。
「改革開始から1年後の2014年にはストライキ寸前の状態になってしまいました。その反省から福利厚生にも力を入れたのですが、2016年の代表取締役就任以降も、『社長1人でがんばってください』と次々にスタッフが辞めていく状況を変えられず、中には下駄箱の私の靴に退職願を入れて去ってしまう人まで……。チームワークってなんなんだ、どうすれば会社をひとつにまとめられるんだ、と必死に考えました」(岡崎氏)
 実際に現場でkintoneを使用している様子
実際に現場でkintoneを使用している様子
そんな試行錯誤の中、岡崎氏の目に留まったもの。それがkintoneでした。バラバラな情報が1つのフォーマットで1か所にまとまれば、部門の垣根を越えて、業務の進捗の可視化やノウハウの共有が進む。コミュニケーションが活性化され、スタッフの意識が統一される。岡崎氏の目指すチームワークを、kintoneなら実現できると考えたのです。
2018年、kintoneの導入に踏み切った岡崎氏。ITとは無縁の牧場で始めた改革だけに、当初はスタッフの間で戸惑いや反発もあったそう。しかし、ITに強い新卒の採用を始めたこととも相まって、kintoneの利用は社内で次第に定着していきます。
同社はまず、牛の生年月日・導入価格・肥育履歴・販売価格・死亡など、従来バラバラに管理されていた牛に関する情報を一元管理する「牛管理台帳」をkintoneで作成。それらの情報をスマートフォンで、いつ、どこからでも確認できるようにしました。
また、それまで手書きだったレストランや売店の日報もkintoneへ移行。手の空いたときに各部門の日報をチェックし、リアルタイムに現場の状況を把握できるようになった、と岡崎氏はいいます。
「たとえば、牛が死んでしまったり、売上が落ち込んだりした際には、kintoneのデータをもとに要因を推定して即座に対策を実施し、効果を測定した上で、次の経営判断を的確に下せるようになりました」(岡崎氏)
「無添加のおいしいお肉を自分たちの手でお客様に」という至高の目的のもと、全スタッフの協力を得て、すべての情報をkintoneに集約した同社。まさに岡崎氏の思い描いた、ひとつの“チーム”としてまとまった瞬間でした。

- 各部門から紙やExcelで報告が上がってくるが、不足や欠落が多く、経営判断に使うデータとして不十分だった
- 部門同士の情報共有が一切無く、同じ会社の社員同士なのにお互いが無関心だった
- kintoneに情報を集約することで、正確なデータをリアルタイムに把握できるようになった
- 社内のkintoneをオープンにして他部門の情報も自由に見えるようにした結果、従業員の意識改革を実現した
実は当初、同社では、アプリに権限を設定し、各スタッフがkintoneで閲覧できる情報を限定していました。全スタッフに会社の状況が筒抜けになるのは恥ずかしい、お互いの悪いところが見えると衝突が起きそう、という考えがあったからです。
しかし、kintone導入のそもそもの目的は、情報共有によるコミュニケーションの活性化と、それによる会社としての連帯意識の向上、チームワークの改善にあったはず。その矛盾に気づいた岡崎氏は、各拠点の売上状況や報告書、岡崎氏からのフィードバックに至るまで、すべての情報を全スタッフに開放することにしました。
すると、スタッフの意識と行動に大きな変化が表れました。「○○店は客単価が高くてうらやましいですね、うちは客数では2倍勝っているのに……」「お客様からこんなご意見があったみたいですね」など、部門をまたいで情報が自然に往来するようになったのです。
「発言している当人は意識していないかもしれませんが、これはつまり、kintoneの情報を各スタッフが自主的に確認しているということ。その結果、『自分や自分の部門ももっとがんばらなくては』という、いい意味でのライバル意識が芽生え、全社的に士気が上がっているのです」(岡崎氏)
情報を1か所に集めて共有化することで、スタッフの意識や行動が変革され、チームとしてさらに強くなる。kintoneでそんな“化学反応”を起こした岡崎氏は、最後にこう語ります。
「弊社にとってkintoneは、正確なデータをリアルタイムに把握する手段であると同時に、スタッフ同士のコミュニケーションを活性化する手段でもあります。業務内容が多岐に渡る6次産業の弊社にとって、kintoneは新たなチームのカタチとなりました。今後は情報の流れを加速させ、チームワークをより強固にしていきたいですね」(岡崎氏)
ITの活用面で発展途上にある畜産業界において、バラバラだった情報をkintoneでひとつにまとめ、“強いチーム”を作り上げたゆうぼく。全国の牧場がその改革にならう日も、そう遠い未来ではないかもしれません。